�v�����܂���2008.7�]12��
2008.12.27�@�o��݊��@
�����ł͂悭�s�o��݊��t�Ƃ������t���܂��B
�u�o�v�͂��q�̂��ƁA�u��v�͒���̂��ƁB
������o�����ď��߂ċq�݂̍�l��������A�q���o�����ď��߂Ē���݂̍�l��������B�܂�A���݂��̗�������ꂼ��o�����Ă݂�A���݂��ɑ���݂̍�l�A�C������������Ƃ������Ƃł��B
�����ɏ����ꂽ�q�́A������̋C�����Œ�����h�����A�܂�������q�����̒B�l�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA�S�̂����ł͒B�l�ƌh���E�E�E���ꂪ����Ԃ�A�q�Ԃ�Ȃ̂ł��B
�܂�A����̗���E�C�����ɂȂ��Đڂ���Ƃ������ƂŁA����͂܂������u�v�����v�̐��_�ɒʂ��܂��B
���́u�o��݊��v�͒����Ɍ��炸�A����̗F�l�W�A�v�w�W�A�e�q�W�ȂǕ��L�������܂��B���̐��_������A����ɂ��܂肫�����t����������A�s�����ȍs�����Ƃ邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B
�����́@�����_�O�菇���w��ł���悤�ł����A�m�炸�m�炸�̓��Ɏ��͂ɑ���u�v�����v��u���荇���S�v�������Ă���܂��B���̐��_�͂܂���������ʗl�̘̂т̐��_�ł�����Ǝv���܂��B
���������ꂱ��40�N�ȏ����Ă��āA�悤�₭�����Ă�����̂�����܂��B
![]()
new2008.12.03�@�������ꌾ
�����̌m�ÂŁA���ɂƂ��Ċ������ꌾ���Ă���������������������Ⴂ�܂��B
�m�Â��I����āA�������Tea Break�����Ă������̂��ƁB
�������m�ÂɌ��������̕��́A���^�C�A����Ď�����낢��y����ł�����������ł��B�ՁA�w����ɒ��������B�m�Ó��ɂ͂�����ƒ����ł݂��A�}�Ɂu�����́����̂��_�O�����܂��傤�v�Ǝ��������Ă��A������Ɨv���v���������������_�O������܂��B
�����č��������������Ⴂ�܂����B�u���낢�������Ă��܂������ꂼ��F��ԁB��������ԁA�w����ԁE�E�v�ƁB��ɗD��������ɂ��ꂼ��Ɉ�ԂƂ����C�����Ŏ��g��ł���������p��ڂ̓�����ɂ��āA���͊������Ȃ�܂����B�����ɂ�����Ɣ��Ȃ��B������ɏ��������Ă���̂ł����A���̒��ł́u��������ԁB�����͓�ԁv�ƗD������Ă����̂ł��B�����̐搶�ɍ��܂Ő\����Ȃ����Ƃ����Ă����Ƒ傢�ɔ��Ȃł��B
���Ȃ݂ɁA���̎Ⴂ���́A���߂�����Ă�����������������A�ǂ����Ă����x�݂��ꂽ�肷�邱�Ƃ�����܂��B���͂��̂悤�Ȏ��ɂ́A�s���d������ԁA�����͎�̂��Ƃ����疳������Ȃ��łˁt�ƌ����Ă��܂����B���F��̂��Ƃł�����A�Z��������������x�{���Ƃ肽���Ƃ��ɖ����ɂ��m�Âɗ����Ȃ��Ă��E�E�E�Ƃ����l������ł��B
�d���Ǝ�ł͈Ⴄ�Ǝv���܂����A���F��̂��Ƃł����Ă������̂��̕��̈ꌾ���A���̒��������������邱�Ƃւ̗�݂ƂȂ������Ƃ͎����ł��B
![]()
2008.11.16�@����
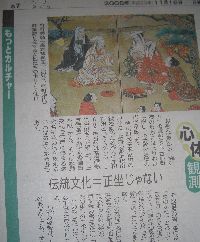 �����̒����i�����V���j�ɖ�c���p�����́s�`������=��������Ȃ��t�Ƃ����L��������܂����B
�����̒����i�����V���j�ɖ�c���p�����́s�`������=��������Ȃ��t�Ƃ����L��������܂����B
�喼�ɒ����w������Ă����ЋːΏB���������w�쏑�ɂ��ƁA�����̐����ȍ�������u���ĕG�v�ł���Ə�����Ă��邻���ł��B
�ΏB�̒��͐痘�x���j�̓�������`��������̂ŁA�u�_�O�̎p���͖{���̌`�͂����Ă��A�`�ɂƂ���ċ����Ȏp���œ_�O��������������̑̂ɍ������p���A�܂莩�R�̂œ_�O�����邱�Ƃ̂ق����ނ���悢�̂ł���v�Ɠ����������Ă��������ł��B
�����͑�ϗ��h�ȑ̌^�����Ă��āu���ĕG�v�����Ă��_�O������ƁA����o���������G�ƂԂ����Ă��܂��A�ЕG�����ɓ|�����u�������v�ł��_�O�����Ă����Ƃ����̂ł��B
�喼����̂����ł́A�喼�ɖ����������Ă͂����Ȃ��Ƃ����z�����K�v�ł������Ƃ������������܂��B
��������̎��G���u���Y�ϕ��}�v�̎ʐ^���ڂ��Ă��āA���̒��ōg�t�������Ă��鏗���̍�����́A�ˊO�Ƃ������Ƃ�����܂����u���ĕG�v�A�u�Ӎ��v���ł��B
�L���́A�`�������̂��̂ł��{���̎��R�Ȋy�Ȍ`�ɖ߂����ق����悢�̂ł͂ƌ���ł��܂��B
���ݒ����̌m�Â͒j���Ƃ��u�����v�B���́u�����v���ŏ��ɍ������˂Ȃ�Ȃ��֖�ł��B���S�҂ɂƂ��Ă͔������_�O�����邱�Ƃ��瑫�����тꂽ��ɂ��Ȃ�܂��B����m�Â��d�˂Ă������ɒ������������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ͂Ȃ�܂����A�h�����ł��B
���̂悤�ɉ��N�����������Ă��Ă��A�N���d�˂�ɂ�Ē�������������Ƒ����݂�����A�ɂ��Ȃ�܂��B
�㋉�̂��_�O�ɂȂ�ƁA�ЂƂ̂��_�O�ɏ��ꎞ�Ԃ�����A���_�O����������q���܂������ɂ��Ȃ�܂��B��������炦�Ă��_�O�����邱�Ƃ��C�s�̂ЂƂ�������܂��A���̌��N�ɂ͗ǂ��Ȃ��̂ł́H�Ǝv���܂��B�����A���N�z�ŕG��ɂ߂��������������Ⴂ�܂��B
���Y�֍l�Ă̍���I�́A���ɒj�����������h���A�������h�����邱�Ƃ���l���o���ꂽ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����͉䖝�����̂łȂ�Ƃ����������Ă��܂����A��̕��������Ȃ��Ȃ��Ă��錻��̏Z������A�������h���Ē�������߂�����o�Ă���̂ł͂Ɗ뜜���Ă��܂��B
�����͍D���Ȃ̂ɐ����������E�E�E�E����Ȃ��ƂŒ�������߂�̂͂��������Ȃ����Ƃł��B���Ƃ����āu���ĕG�v�ł��_�O������킯�ɂ��������E�E�E��͂藧�玮�����̂��_�O�������Ƃ��낢��ƌ��ɍl���Ă��������������̂ł��ˁB
![]()
2008.10.25�@����q����̌�����
 ����q����̂��������ɏ�����܂����B�ꏊ�͔����̊i�������z�e���B
����q����̂��������ɏ�����܂����B�ꏊ�͔����̊i�������z�e���B
���͒����̐搶�Ƃ��ď�����Ă���̂Œ����ŏo�Ȃ���̂��X�W��������܂��A���c�}���}���X�J�[�E�����o�R�d�Ԃɏ���Ă����̂ŁA�m���i�����O�h���X�j�������Čy���ŏo�����܂����B
���A�����͍g�t���̊ό��q�ł����ς��ł��B�v���U��̏����s�ŁA�S�̓E�L�E�L���Ă��܂��B�{�m���ɉ��肽���ā@��������3���قǂł��̃��j�[�N�ȑ���̃z�e���������܂����B���݂̌����͑吳����̂��́A�ٓ��͌Â����ɂ��i���̂�����̂ŃA�[���f�R���ł��B
�}���Œ��ւ��Ĕ�I�����̂ق��ցB�m���Ă�����͈�l�����Ȃ��̂ŁA�T�����ň��ݕ������������Ȃ���Â��ɑ҂��܂����B�����Ă��悢���I���̉��Ɉē�����܂����B
����q����ł���V�w�ƁA�V�Y�̓���ł��B�E�F�f�B���O�h���X�p�̐V�w�̉��Ɖ��Ŕ��������ƁB�V�Y�����肪���̂���f�G�ȕ��B�e�����F�l�Ɛe���ŏj�������Ȕ�I���ł��B���̃e�[�u���ɂ͗F�l�̕��X�����炵�Ă��āA�����Ă݂�Ƒ���L������V�����ł��炵���Ƃ̂��ƁB�f�G�Ȃ��F�B���ƈꏏ�Ɋy�������Z���w�����𑗂��Ă����l�q��������܂��B�����������������Ă��邤���ɁA�����̗F�l�ɃG�X�R�[�g����Ă��F�����ɂ�����܂����B�F�l�̃G�X�R�[�g�Ƃ����̂���������͂荡���Ȃ̂�����Ɗ����܂����B
�V�w�����F��������Ă���ԂɁA�V�Y�V�w�̏����������獡�܂ł̎ʐ^���傫�ȉ�ʂŎʂ�������A���̒��ɂ͋��N�̂�����̎��̂��̂�����܂����B
�����������Ă��邤���ɁA�����p�ɂ��F�����������V�w�̓o��ł��B�܂������p�����ł₩�ʼn����ԉŁB
�F�l�������悤�ȏj�����{���ɂ��K���ȃJ�b�v���B���������̂����ŁA�����������ꂪ�܂������Ȃɉ����Ă��������āA�F���܂Əj���ł���ϊ��������Ƃł����B
�A��͂��y�Y���R�����A���Ԃ܂Œ����āA�����I�ȑf���炵����������I���̗]�C���y���݂Ȃ���A�s�y�q�œ��키�����H����ɂ��܂����B
����q����őg�R������Ă�������������������̂ŁA���̕��ɍ����̐V�w�̂��j���Ƃ��đђ��߂�����Ă����������j�ɓY���܂����B
�{���ɂ��߂łƂ��������܂����B���i�����K���ɁI
![]()
2008.10.14�@�t����������������
����̌m�Ò����ɐ��������āA�킽���̒����̐搶������ɒ����ɂ��������܂����B�搶�̑��A�В��̕�3�l���A�q�Ƃ��Ă��������܂����B������d�Ȃ��ē��̂��莆�������āA�F�l����f�G�Ȃ��Ԏ������������܂����B�搶�͂�������87�A�F���܂�70�Έȏ�̕��X�ł����@�������ł��炵�Ă��������ƂĂ��������܂����B�G�߂͏����炸�A�����炸�̍D�G�߂ł��B
��ɂ����������ł���A���|�ҍ�������܂����B�O�Ȃ̂����͒W�������10�N�L�O�Œ������[���@�W�搶�̂����M�s�������M�l�t�̐�������̂��q���܂s�l���������Ă������������̂ł��B���͏��ԓ����̂܂Ƃ߂����̂ɖ��X�d���̂��`�B�撣���č�����I����̎ϕ��B���ꂩ�珬�z�����ɗ������B
���ꂩ�珉�Y�B�����^�b�v������Ă������̂ʼn��������X�B�����q���ɏo������A�����Ɂs�����ȁt�̎�َq�����o�����āA�������ƂȂ�܂��B
���������グ�ďH�����R���ꂽ�Ԃ����𒆓B�ɂ����܂����B�s�_�I�����炦�āA�����B�g���̃t�W�o�J�}�E�z�g�g�M�X�E�X�X�L�E�~�Y�q�L�E�썮�e���ƂĂ��D�]�ł����B
���悢�撃���̃��C���̂��Z���ł��B���q���܂�5�l�i���l�ɂ͂킪�Ƃ̃x�e�������k����ɂ��Ă��������܂����j�ł����̂œ�q�ɕ����ē_�Ă܂����B���ʂł͑��������Ȃ̂ł����A�F���܂̂��ݑ��ɋC���͂炢�A�����͗���ɂ��܂����B
�������̖n�G��`����������,�a�h�_�B���َq�͘a���̐܂莆�ō�������ɐ���ޓ���A���D���Ȕ�������Ă��������܂����B�J�����Ƃ��ɊF���܁u����[���Ă��v�Ɗ������E�E�E�B
�\�t�@�[�Ŋy�ɍ����Ă��������ĊF���܂ɂ����������オ���Ē����āA���������͏I���ł��B
�搶���������ɂ���������Ƃ����v���������Ƃ����܂������A�F���܉������C�����悭������Ă��������A�����ƂĂ����ꂵ���A�Y����Ȃ�������ƂȂ�܂����B
�p�ӎ����Ŗ]�ς�ł������U��Ԃ�Ƃ��낢��ƍs���͂��Ȃ��_������A�{���ɒ����̒�������邱�Ƃ̓�����������܂����B���܂łɌm�Ò����͉�������܂������A�����̂悤�ɊO�̕������������Ă̒����͏��߂āE�E�E������J���Ɩ������𖡂킢�܂����B
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
![]()
2008.10.10�@���K�����{
���y�̕�����A�ÓT�Ƃ������鏬�K�����{��2��ޒ����܂����B
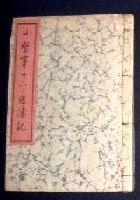
 1���ڂ͉��Ǝ������ꂽ�N�A���a19�N2���ɔ��s���ꂽ���̂ŏ���2000���Ƃ���܂��B���i��3�~15�K�B�����ȑ�́u���K���\�Z�����B�L�v�i�꞊���[���s�j�B�@�����14��W�X�ւ������������Ă�������Ⴂ�܂��B�����͂���܂�������̘̂a�Ԗ{�A���ŒԂ����Ă��܂��B�}�G���f�p�Ȏ菑���A���������́B
1���ڂ͉��Ǝ������ꂽ�N�A���a19�N2���ɔ��s���ꂽ���̂ŏ���2000���Ƃ���܂��B���i��3�~15�K�B�����ȑ�́u���K���\�Z�����B�L�v�i�꞊���[���s�j�B�@�����14��W�X�ւ������������Ă�������Ⴂ�܂��B�����͂���܂�������̘̂a�Ԗ{�A���ŒԂ����Ă��܂��B�}�G���f�p�Ȏ菑���A���������́B
�_�O�����͊T���ł�����������Ƃ���͂����Ƃ������āA�r���ɂ́s�����ɏA���ĐS���t�Ƃ������ڂ�����܂��B�����ɂ́s�����Ȃ��Ċ����ƂȂ��ׂ��ɂ��炸�A�ڍׂ͕M���̐s�������A���n�Ɏt�ɏA���ċ��������m�Â��܂�邱�Ƃ�ؖ]������̂Ȃ�t�Ƃ���܂��B
�����P���́u���K�B�ډ��v�i��@���@�w���E�l�{�@�r�@�ҁj�B�i�W���Д��s�j����͏��ł����a27�N�A�������{��10�ł̂��̂ŁA���i��250�~�B���̋����{�͔����ʐ^�̓_�O�̎ʐ^�����\��R�ڂ��Ă��āA�����̂ł͂���܂���B
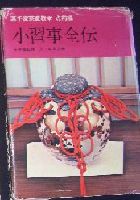 ���́u���K�B�ډ��v����{�ɂ��Ăł����{�������w������Ɋw�u���K���S�`�v�i�W���Ёj�ł��B���i��500�~�ł����B
���́u���K�B�ډ��v����{�ɂ��Ăł����{�������w������Ɋw�u���K���S�`�v�i�W���Ёj�ł��B���i��500�~�ł����B
���݂̏��K���̖{�́A���_�O�̏������A���ʐ^�̂悤�ɏڂ����ڂ��Ă��āA�S����3���ɂȂ��Ă���悤�ł��B
���̋M�d�ȋ����{�������������͍�80�߂��̂ł��B������60�N�ȏ�����Ă���������A���Ă͋����Ă��炵���̂ŁA�������̓_�O�ŋC���������Ƃ�Â��ɒ��ӂ��Ă�������L����y�ł��B���̕\���������ӂŁA�W���J�����_�[�����Ɏd���Ăĉ����������Ƃ�����܂����B���M�S�ŁA�����̋����{�ɂ͉��M�����ł��̕��̃�������R�������܂�Ă���A������ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��B���̕��̒����̗��j�������p�����Ă����������悤�ŁA�������ꂩ��܂��܂����i���˂Ǝv���܂��B
![]()
2008.10.�P�@�m����
�����܂ʼnJ�������̂ŐS�z���܂������A�J���ߑO���ŏオ��z�b�Ƃ��܂����B
�����͌m�Ò����̓��B�����͎�������������܂����A�����̓x�e�����̐��k��������ł��B�����ƒ����̈ē��̎莆���o���Ă��������܂����B����̏����A���Η����͎������āA����̕��ɂ͂��َq��p�ӂ��Ă��������܂����B���q���܂�3�l�B
�����̌m�Ó��̊�Ԃ�ł����A�����͊F���ܒ����ł���������A�m�Ò����Ƃ͂������͋C�͊����H�ł�
���F�̒����́A�������Y�����������Z�������������Ɛi�݂܂��B���Y�܂łɉ����₦�Ă��܂��Ă͑�ςȂ̂ʼn���7�قǂ����������܂����B
���ꂪ�ǂ������̂��A�Z���̍��ɂ͂����̎ς����ƂĂ��ǂ��A��ϔ����������Z�������Ƃ��ł��܂����B�����͂��Z�������C���A�����������Z���������グ�邽�߂ɉ��Γ�����킯�ł�����听���ł��B�F���܊���Ă���������A3���ԂقǂŏI���܂����B
����Ɛ��q�̑����s�b�^���A�A�q���f���炵���q�Ԃ�łƂĂ��ǂ��u��������v�ƂȂ�܂����B
�u�o��݊��v�Ƃ������t������܂����A���������Ă݂���A���q�ɂȂ��Ă݂��肵�Ă��݂��ɂ��݂��̋C�������������A�v�����̋C�������ł�Ƃ������Ƃ��ǂ����������Ǝv���܂��B
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
![]()
2008.9.23�@������������
���̒��A���ł��s����t����BTV�ł��N�C�Y�ԑg���嗬�s�ł��B
����Ƃ����̏H����u������������v���n�߂�悤�ł��B���������ď��N�x�̍��N�͂R,�S���̎��������{����Ƃ̂��ƁB
���i�̒����̌m�Â͓_�O�̌m�ÂɏI�n���āA���_��w��͎����I�ɕ������Ȃ���Ȃ��Ȃ��w�Ԃ��Ƃ��ł��܂���B
�������A�_�O�����Ă������ɂ��낢��Ƌ������L����ƂƂ��ɁA���낢��^�₪�킢�Ă��āA�s�����͂ǂ������킯�ł�������̂��낤���t�Ƃ��A�s���̂�����͂�������g����悤�ɂȂ����̂��낤���t���A���ׂĂ݂����Ȃ�܂��B�m�Ï�ł��������搶�ɂ��q�˂��邱�Ƃ݂͜�܂��B
�����ɂ͂��낢��Ɓu��������v�u���܂�v������A������x���_�I�ȗ��t�����Ȃ��ƒp���������ƂɂȂ�A�����K�v�ł��B
�܂����������Ă��Ȃ������璃���̂��Ƃ����낢��q�˂��āA�����ɋ����邱�Ƃ�����A�Ȃ̖��m��p����������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�ƌ����Ă������͑����|�p�ł���̂Ŏ���͈͂��L���A���X�����Ă��s���鎖�͂���܂���B
�����ċߔN�@�F���܍��w���Œm���~�����̎���B�������_�O�̎��H�����ł͕�����Ȃ��������Ă���̂łͥ���Ƃ����ϓ_���獡��́u������������v���n�܂����̂�����Ǝv���܂��B
������������̌���HP������Ɨ\�z�����o�Ă��܂��B�R,�S���͂ق�̏����I�Ȗ��B�����S�������i�����̂łͥ��Ƒz������܂��B
���ł������̒����C�Ǝ҂���ɂȂ��Ă��ǂ��Ȃ��ł����A�u���v�u�w�v�u���v�o�����X�̂Ƃꂽ�����C�s�҂ɂȂ肽���ł��B
![]()
2008.9.15�@�����̈��ݔ��
�a�J�ɂ���u�����Ɖ��̔����فv�ŊJ��30���N���L�O���āA�u�l��n�D�i�ɂ݂�n�݂̕����j�v�W�����Ă��܂��B
�l��n�D�i�Ƃ́A�s�^�o�R�t�s���t�s���t�s�R�[�q�[�t�ł��B
�s���t�̎��ɂ͕q���ɔ������鎄�E�E�E���傤�Ǎu������s������Ȃ̂ōs���Ă��܂����B
�u�i���{���L�v�̓W������n�܂��āA��������A��������Ȃǂ̒���A��������A���t��A�o�������̍���x���i���ꂪ�A���A���A���͗l�łƂĂ��A�[�g�j�A���E�̒��̓���A��r�̃��x���A����A�R�[�q�[����҂������J�b�v�A�^�o�R�~�ȂǁA�܂�����������`�[�t�ɂ��������G���W������Ă��܂����B
 �u����́u���{�l�Ƃ����v�Ƃ����e�[�}�ŁA�u�t�͓��Ԕ����يw�|���̍H���@�G���B
�u����́u���{�l�Ƃ����v�Ƃ����e�[�}�ŁA�u�t�͓��Ԕ����يw�|���̍H���@�G���B
�ȉ��͍u�����e�̈ꕔ�B
�������ނƂ����L�q�ŌÂ��̂͂Ȃ�Ƃa�b�T�X�N�A�����̓z��̘J���_�B���̍��́s���t�Ƃ��������s䶁t�ɂȂ��Ă��܂��B���{�̋L�q�ł́s���{��L�t815�N�ɋߍ]���ߎ��ō���V�c�ɂ����������グ���Ƃ����L���ł��B�܂��s��ȋ��t�̎����̓�������Ŗ�Ƃ��Ē������Ƃ����L�q������܂��B
���̖̓��u�ցA�T�U���J�ȂǃJ�����A�ȁB���͂��̗ǂ���n���D�݁A�N�ԕ��ω��x�P�R���ȏ�ō~����1300�o�A�~�̋C��2.3���ȏ�̂Ƃ��낪�悢�����ł��B
���{�̖k���n�т̂����͏H�c���\��s�́u�O�R���v�A��錧��q���́u���v�����v�A�V��������s�́u���㒃�v�A��ʌ����Ԏs�́u���R���v�B
�����Ă���4��̐������u�t�̕������矹��Ă�������A���u�Җ�60���قǂɎ��������Ă��������܂����B
�����z�́u�O�R���v�E�E�E�E�W���Ȗ��A�Ɠ��ȍ���A��Ō��ɊÂ݂��c��
�@�@�@�@�@�@�u���v�����v�E�E�E�E�a�݂�����A�R�N������
�@�@�@�@�@�@�u���㒃�v�E�E�E�E�E�ꖡ�����邪�������A�Y�n���𗦍���������������
�@�@�@�@�@�@�u���R���v�E�E�E�E�E�ΐF�A��������͂܂�₩�����X�g�����O�A��ɊÂ݂��������c��
��������������ł��ꂱ��3���ԋ߂��u����ł����B
![]()
2008.8.20 �@�����̊y���ݕ�
���鐶�k���珋���������܂����B���̕��͒����������āA��������������Ă�����ł��B
���̕������C�Ȃ��{���̗]���̂悤�ȂƂ���ɁA�w�����͂����Ɋy���߂Ηǂ��̂��A���ɂƂ��Ă͉ۑ�ł��x�Ə�����Ă��܂����B
�킽���̓h�L�b�Ƃ��āA�h���^����ꂽ�悤�����܂����B
��������������Ă�����Ȃ�ł͂́@���̉ۑ�B���i�̌m�Âł͍��܂ł̓_�O�̌J��Ԃ��B�_�O�͉���ނ�����܂����A���F��F�̋G�߂ɂ���ĈႢ�܂����畜�K����ł����A��͂蕨����Ȃ��Ȃ��Ă���̂��Ǝv���܂��B
������܂ł̒i�K�ł́A���[�����~����Ă���܂����A�����܂Œ����ƃ��[���͂Ȃ��Ȃ�܂��B��������͎����Ȃ�̏C�s�ɂȂ�܂��B
�����́s���ĂȂ��t�̕����ŁA��������{�B�����͂��q���܂������ɂ����ĂȂ������邩�A�e�[�}�����߁A����̎�荇�킹�A���A���َq���ɂ��čl����̂ł����A���ꂪ����Ƃ��Ă͑�ϊy�������Ƃł��B����������ƂȂ��Ē���������Ƃ����@��́A����ł͂��܂肠��܂���B�m�Ò����Œ���������邱�Ƃ͂���܂����A����̎�荇�킹����|���A�������ׂĂ�����Ƃ������Ƃ܂ł͂Ȃ��Ȃ��E�E�E�B
����������ŁA���q���܂����������鎞�͂��ꂱ��l���܂��B���̎��ɒ�������̃q���g�A�S������A���I�Ȃ����ĂȂ�����������邩������܂���B������y�������Ƃł��傤�B
���̂�������y�����ł��B���Ƃ������̂��ĂȂ��ł��F�Ŗ������S�����Ă��q���܂Ɉꕞ����������C�x���g�B
�܂��A������������邱�Ƃ��㋉�҂ɂƂ��Ă͊y�������Ƃł��B���݂��ɋC�S�����킹�ă��[���ɏ]���čs���y�������ƁB����͏C�s�Ƃ������A�Q�[�����o�Ŋy�����ł��B
���H�����łȂ��A���_������邱�Ƃ��y�������ƁB����͎����Ȃ�̕��ɂȂ�܂��B�{��ǂ�A�u�����ɂ�������A���p�ق֏o��������A�悻�̂�����ɂ����Ă������q��������E�E�E�B
�s���t�s�w�t�s���t�E�E�Ƃ悭�����܂����A���̂R�������Ȃ�Ƀo�����X�悭�K�����邱�Ƃ��A�������y���ތ��ƂȂ�̂ł͂ƁE�E�E�����̂����̎��̎v���ł��B
![]()
2008.7.29 �@�����͋Z�p�H�w��H
�u�����͈�̉��Ȃ̂�����H�v�Ǝ��X�v���Ă��܂��܂��B
���������s���t�Ƃ͉��Ȃ̂ł��傤���H�s���t���t�����͓̂��{�Ɠ��̂��́B�_���E�|���E�����E�ؓ��E�����E�������X�B
�厫��ň����Ă݂�Ɓu�l�Ƃ��Ăӂݍs�����E�����v�Ƃ���܂��B�������_�I�Ȃ��́A�N�w�I�Ȃ��Ƃ����邱�Ƃ͊m���ł��B���ہA�������T�̐��_�E�N�w�������Ă��܂��B
���������i�̒����̌m�ẤA������_�Ă邽�߂̂��낢��ȓ_�O���K�����邱�Ƃɐs���܂��B
�_�O�������������K�����đ̂Ɋo�����܂��A�������邱�ƂŁs�S�t���ł��Ă���ƁE�E�E�B���́s�S�t�ƌ����Ƃ���Ɂs���t�̊T�O���łĂ���̂ł��傤���B
�s���t�������̂ŁA�_���A�����A�|���A�����Ȃǂ́A���Z�ɂ��Ȃ���̂Ȃ̂ŁA�Z�p�̏�B���d���܂��B�m���ɂ��܂��l�Ɖ���Ȑl�̈Ⴂ�E�����������͂����茻��܂��B
�������Z�p�ł��傤���H
���_�O�̎p�E�`��A������_�Ă���A�������肷��Z�̏��E����͑����͂���܂����A�Ⴂ�͂���Ȃɂ͂����茻��܂���B����������ɓ_��������A�����Ƃ������̂ł͂���܂���B
�������A�_�O�͏������w�Ԃق��ɁA�`���ׂ������܂肪����A�����ɔ������_�O�����邩�A���邳���قǍׂ����w�т܂��B
5�{�w�͂��낦�ď������܂Ƃ߂�Ƃ��A�ӂ����̎J�����A�함�̐��ߕ��A�������A����̎������A���ۂ̍\�������X�E�E�h�d���̋��h�̂悤�ȍׂ����Ƃ���܂ŁA���������������悤�v������܂��B
���̂悤�ɍׂ����Ƃ���܂ŋC��z���āA�_�O�̌m�Â��J��Ԃ����ƂŁA����̈������A�D��Ȑg�̂��Ȃ��A�W���́A���q���܂Ɏ���̂Ȃ��悤�ɂ����@�A����ɑ���C�z��A���ĂȂ��̐S���E�E�E�s�S�t������Ƃ������ł��傤���B
���́s�S�t�́A�������m�Â��Ă��Ȃ����ł��������킹�Ă��������R��������Ⴂ�܂��B���ق̏�������A�z�e���}���A�������X�g�����̓X�����A���q���ܑ���̂�����������Ă�����X�E�E�E�B
�m�Â����Ă��Ă��A�ڂɌ����Ă����ς���Ă�����̂ł͂Ȃ��A����Ƃč�i���o����킯�łȂ��A�x���y��̌m�Â̂悤�Ȕ��\�������܂���B�h�m�Â������h"��B�����h���Ȃ��Ȃ�������ɂ������̂ł��B
�����������������m�Â��邤���ɁA���낢��Ȃ��Ƃ�m�肽���Ȃ�܂��B������̂��ƁA�T��̂��ƁA���Ԃ̂��ƁA���j�A�l�G�܁X�̍s���A�G�߂̂��ƁA��̂��ƁA�A�z�̂��ƁA�\�̂��ƂȂǁE�E�E�ǂ�ǂ�m���~���łĂ��܂��B���̈Ӗ��ł́s�w��t�I�ȗv�f������܂��B���ׂ悤�Ǝv��������ł��e�[�}�͏o�Ă��āA���ׂ���̕��@���{�����܂��B
���̂������ŁA���Ȃlj���40�N�߂����O�����ɁA�����Ɋւ���Ă���̂ł��B�������y�����E�E�E�B
���ǁA�����͓��풃�ю��̂��Ƃ��A�����Ƃ����g�g�̒��ŋX�����s���Z�p�ł�����A�N�w�I�Ȃ��̂ł�����A�w��I�Ȃ��̂ł�����Ƃ������Ƃł��傤���B
������40�N�߂����Ă��鎄���u�����͈�̉��Ȃ̂�����H�v�̓����͓���A���ɂ͏d���߂���i���̃e�[�}�ł��B
![]()
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@HOME