![]()
new2015.06.24 名水点
 「名水点」の稽古をしました。
「名水点」の稽古をしました。
現代では東京ではそのまま飲むことができる井戸水は無いと思います。国分寺にあるお鷹の道の《真姿の池》の湧水は結構飲むことができるとのことです。
今日は釣瓶の水指にペットボトルの「谷川の大清水」を入れました。
釣瓶の水指に注連縄・御幣の飾り付けがしてあれば《名水を用意しました》という亭主の無言のしるし。亭主からは間違っても《今日は名水を用意いたしました》と、でしゃばっては言いません。客が飾り付けを見て亭主の心遣いを察知して「今日は御名水をご用意していただきましたようで、ぜひ頂きとうございます」と言うのです。
「どちらの名水でしょうか」という客の問いかけに、「《真姿の池》の湧水でございます」と答えたりし、客も「それはそれは遠いところお運び頂き有難うございました」などとまことしやかに言ったりしました。
しかし注連縄と御幣をわざわざ飾るので、やはり御神水でなければならないのではと思いました。御神水といえば神社の湧水。
研究会等では「明治神宮の清正の井の水でございます」と答える場合が多いです。
ある方は「茶道は禅宗・キリスト教のほかに神道も入っているのですね」とおっしゃいます・・・・確かにこのお点前はそうです。
「現代の名水点ではペットボトルでも海外の珍しいミネラルウォーターや、1リットル1000円もする特別な水を使っても良いのでは」「○○の水を取り寄せました・・はだめでしょうか?」などいろいろ名水談義でもりあがりました。
そういう水もちょっと飲んでみたいですね。
また柄杓で汲む水の量はどれくらいにしたらよいのであろうかということになりました。一人3口位飲める量が良いのではと思います。
この「名水点」は今や”稽古のための稽古”という感じです。
![]()
2015.06.20 行之行台子の稽古
 「行之行台子」の稽古をしました。
「行之行台子」の稽古をしました。
奥伝なので、普段の稽古とは別にこのお点前ができる方だけでしました。
水曜クラスは5人、土曜クラスは4人が該当されます。習熟度が上がって来た生徒さんが増えて嬉しい限りです。
「行之行台子」のお点前は「唐物」と「台天目」のお点前がしっかり出来ていれば理解が早いです。
帛紗のたたみ方で下端を取る場合がでてきたり、風炉では柄杓を釜に戻すとき、置柄杓と切柄杓が交互になります。柄杓の置き方にも真行草があり、草の引き柄杓はこのお点前ではしません。
 唐物道具と和物道具が混ざった道具組です。茶碗・茶入は唐物。茶杓は元節の竹で和物、しかし清めるときは象牙扱いになります。
唐物道具と和物道具が混ざった道具組です。茶碗・茶入は唐物。茶杓は元節の竹で和物、しかし清めるときは象牙扱いになります。
茶杓にも真行草があり、元節は行です。
![]()
2015.05.24 《天皇の料理番》で師を偲ぶ
テレビドラマ《天皇の料理番》が放映されています。
あまりテレビドラマは見ない私ですが、この番組は見ています。というのも私が茶道を師事していた先生のご主人様が原作者の”杉森久英”氏なのです。
残念ながら先生は2年前に他界されました。この番組が放映されることをお知りになりましたらさぞ喜ばれご覧になったことでしょう。
そういう意味で 私はこのドラマを先生をお偲びしながら見ているのです。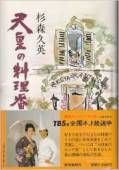
杉森久英氏(明治45−1997)は中央公論、河出書房を経て、小説家になられ「天才と狂人の間で」で直木賞を、その他数々の文芸賞を受賞されています。
ご主人様が自宅で仕事をされていらっしゃるので、編集者の方の出入りも激しく、先生は茶道教室をされつつ、編集者へお茶を出したり大変であったようでした。
先生は茶道を本格的に業躰先生から習われ、若い時から茶道教室をされていました。
ご主人様がお亡くなりになった後「さあこれからは茶道教室を一生懸命しましょう」と思われたそうですが、やはりご主人様の存在が大きかったので、いざその時には気持ちが落ち込んでお出来にならなかったそうです。
そんなお話をご存命の頃いろいろ聞かせていただいていたので、今回このドラマを見ると先生のことが思い出され、ご一緒に見ているような気になります。
![]()
2015.05.17 独特の日本語
本屋さんでちょっと立ち読みした本に”素晴らしい日本語”について書かれていました。作者も本の題名も忘れてしまったのですが、内容が印象に残ったのです。
日本独特の美しい言葉があるというのです。
例えば「お疲れ様」「お世話様」「お陰様」「お互い様」など。そしてちょっと古いものでは「お天道様」。なるほどと共感しました。これらの言葉はなかなか外国語には翻訳しにくいものでしょう。
そういえば、先日安倍首相が訪米した時 オバマ大統領が共同記者会見の折、「OTAGAISAMA (お互い様)」と日本語で言っていました。日本独特の言葉と意識して使われたのでしょう。
これらの言葉にはみな《様》が付いています。相手を気遣い、ねぎらい、感謝・尊重する意味なのでしょう。
実際使うときは、習慣的に挨拶として軽く言うことが多いですが、それでも人と人のコミュニケーションに、大いに役立っていることです。
しょせん、人間は生き物、ねぎらいや気遣いの言葉を掛けられれば嬉しいものです。
「よろしくお願いします」という言葉も独特の良い日本語と思います。以前「もったいない」という日本語も注目されました。
日本語には素晴らしい言葉、表現が沢山あり、誇りを持っても良いと思います。
![]()
2015.05.07 英語で描いた日本
 おととし我が家で収録した、放送大学の番組が今朝放映されました。
おととし我が家で収録した、放送大学の番組が今朝放映されました。
《英語で描いた日本》という科目です。ジョン・ブロウカリング先生が日本の文化等を実際に体験して、大橋理枝先生とトークをするという番組です。「折紙」「義太夫」「座禅」「剣道」「書道」・・などです。
そして「茶道」のレッスンを我が家でなさったのです。
実際にお点前をなさるということで、一回だけご指導しました。お忙しい方なので後は自宅で稽古をするとおっしゃり、私は帛紗、茶碗・棗、茶杓、柄杓などの道具と、昔家元のところで国際茶道セミナーに参加した時の英語で書かれたテキストをお貸ししました。
 本番ではどうなるかと思いましたが、そこはさすがブロウカリング先生、帛紗捌きも滑らかに、諸道具の清め方も、また柄杓を扱う手つきも見事にされました。拝見物を取り込み、茶道口で礼をするところまで一生懸命にされ、客役の生徒さんはじめスタッフの方共々、とても感服しました。
本番ではどうなるかと思いましたが、そこはさすがブロウカリング先生、帛紗捌きも滑らかに、諸道具の清め方も、また柄杓を扱う手つきも見事にされました。拝見物を取り込み、茶道口で礼をするところまで一生懸命にされ、客役の生徒さんはじめスタッフの方共々、とても感服しました。
お点前の後は「茶道」についてブロウカリング先生と大橋理枝先生の私へのインタビューです。
お点前のやり方で自由度はあるか、仕舞い付けまでやる意味は?茶道をすることで日常何か役に立つか? 茶道での基本となる言葉は?など・・・
ブロウカリング先生は今回茶道を体験されて、静かな中茶筅を振る音、茶碗の絵柄、お菓子の形や茶杓の銘で季節感を感じることなど、茶道のtranqulityを感じたとおっしゃっていました。
「茶は喉の渇きを癒し、茶道は心の渇きを癒す」という 私の好きな大宗匠の言葉で私は締めくくりました。
放送大学に出演したことは私にとって多分”一生に一度”のテレビ出演となったことでしょう。
追伸:ブロウカリング先生が2014年春にお亡くなりになったことは大変ショックでした。明るくおおらかで、ユーモアのある大変お元気であった先生のお姿を今朝TVで拝見すると心が大変いたみます。心よりご冥福をお祈りします。
![]()
2015.04.25 新社会人
生徒さんで今年から社会人になられた方がいます。お茶のお稽古は続けたいということで、頑張って通ってくださっています。
環境が今までと変わって、人間関係や、なれない仕事でのストレスもあることなので、《無理しないでね》と私は言っていますが、その方は《お茶に来ることが気分転換になるのです》とおっしゃいます。
土曜クラスの方は学生さんを除いて、全員仕事を持っていらっしゃる方。普段お忙しく働いていらっしゃるので時々、《寝坊したので休みます》とか、《体調不良で休みます》《出張で休みます》という連絡を受けることが多いです。
しかし、稽古にいらっしゃる時は着物でみえる方もあったりで、緊張感を持って真剣に取り組んでおられます。
そしてやはり《お稽古場に来ると、何となく癒される気がする》とおっしゃいます。稽古の後、時間があるときは皆でたわいもない話をしたりもします。そういう時間も楽しいようです。確かに職場と家との往復だけでは、物足りないのでしょう。職場以外の方との会話も気分転換になることなのでしょう。
昨年から社会人になられた方は、確かにこの一年で社会人らしくなられました。今年から社会人になられた方も、きっと日に日に社会の厳しさになれて、しっかりとした社会人になられることでしょう。
私は「食事はバランスよくしっかり摂って、睡眠もじゅうぶんに、健康管理をしっかりね」と、思わず親のように言葉を掛けています。
![]()
2015.04.06 食事会
昨年、私は古希を迎え、古稀茶会をしました。社中の皆さまにはお点前・お運び・水屋などいろいろな役をしていただき、おかげさまで盛会裏に終えることできました。
私は社中の皆さまにこれで十分古稀を祝っていただいたと思っておりました。ところが、今年に入って《先生の古希を祝う食事会を》と言ってくださり、私は恐縮しながらもそう言っていただけたこと大変うれしかったです。
そして昨日、銀座の某鯛めしで有名なお店でその会がありました。
小雨降る中にもかかわらず、着物でいらした方も多く、とても華やかな雰囲気です。赤ちゃんや、小さいお子さんをご主人様に預けてこられたり、お出にくいところ大勢集まってくださいました。
水曜クラス・土曜クラスは去年の教室内茶会や、古稀茶会、初釜で皆様すっかり打ち解けられています。
先日お茶名をおとりになった方の私への温かいお言葉の後、乾杯のご発声で、ピンクのロゼワインで乾杯。
 稽古場ではあまりおしゃべりはできませんが、今日は皆様おいしいお料理に感嘆の声を上げながらおしゃべりに花が咲きます。最後には干菓子と抹茶も出てきました。泡が細かく大変良い服加減、さすが和食プロのお店と感心しつつ美味しくいただきました。
稽古場ではあまりおしゃべりはできませんが、今日は皆様おいしいお料理に感嘆の声を上げながらおしゃべりに花が咲きます。最後には干菓子と抹茶も出てきました。泡が細かく大変良い服加減、さすが和食プロのお店と感心しつつ美味しくいただきました。
最後に私はお礼の言葉とともに、茶道の稽古は、茶禅一味といって禅の精神が入っているので、お点前だけの稽古ではないこと、稽古場を離れても身の回りを綺麗に《日々是茶》の気持ちでと、ちょっと講釈しました。
このように皆様に再び古希を祝っていただき、”これからも一生懸命ご指導をして、皆様とともに人間磨きをしていこう”と強く思いました。次回の賀寿、喜寿を目指して…。
![]()
2015.03.21 茶名許状引渡式
今日、茶名を拝受された方への許状引渡式をしました。
私は30年近く茶道教室をしていますが、茶名を頂いた方は今回が初めてなのです。第1号ということで、私はすごく感激しており嬉しいのです。
茶友の方に後見人になって頂きました。
まず私が「真の行台子」のお点前をしました。このお点前は裏千家では我々ができる最高のお点前なのです。
このお点前は久しぶりなので、私は2,3日前から何回も何回も練習をしました。小一時間もかかるものなのです。練習している姿を見て主人は、「先生なのに練習?」と不思議そう。
その成果もあって スムースにお点前は進み、おいしいお濃茶が練られました。お菓子は七種です。
その後、茶名の許状引渡式をしました。裏千家からは飾帛紗がお祝いとして添えられました。私からは赤楽茶碗をお祝いとして差し上げました。
茶名許状は、重々しく桐箱に入っています。茶名はその方のお名前が当代家元夫人のお名前と同じであるためか、音違いの字が当てられていました。その方はとても明るく陽気な方なのでぴったり宗名と思いました。ご本人も喜んでいらっしゃいました。
時分どきになり、手作りの料理で懐石祝膳を頂きました。主人の実家から頂いた加賀塗の足つき膳を初使いしました。主人も既に顔馴染みになっているので加わり、一緒に頂きました。
午後からは折角設えをしてあるので、茶名を頂いた方に「真の行台子」の稽古をしていただきました。普段はこのお点前の稽古がなかなかできないので良い機会でした。
「あまり《茶名を頂いた》とほかの方にいわないでください。恥ずかしいですから」とその方は謙遜して仰いますが、多分それだけの実力が伴わっていないと感じるからでしょう。私も昔まったく同じ気持ちでした。
許状はあくまでも許し状・・・これから精進すればよいのです。茶道の許状は修了証ではないのですから。
その方もこれを一つのきっかけにますます精進されることでしょう。大いに期待しています。
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
![]()
2015.03.11 3.11を「三友の式」で悼む
今日は3.11、東日本大震災が起きた日です。早いもので今年で4年経ったことになります。
私はあの日、地下にあるスーパーで買い物をしている時、揺れを感じました。初めは立ち眩みかしらと思いましたが、天井からぶら下がっているものが大きく揺れて、スーパーの店員さんも中から飛び出してきて大騒ぎとなりました。地下でこんなに揺れを感じたので、地上はどうなっているか心配しましたが、地上は特に変わっていませんでした。
帰ってから家の中を点検しましたが、2階の本棚から本が数冊落ちていたり、仏壇の像が傾いていたりしていました。そしてTVを見て東北地方が大変なことになっていることを知りました。そしてその何分後かに、あの傷ましい津波の画像を見ることになりました。
それだけではありません。それから数日間、福島原発の事故を目の当たりにすることになりました。
原発事故は今でも大変深刻な状態です。この事故を経験するにつけ、原発は本当に止めるべきと思います。
つい先日ドイツのメルケル首相が来日しました。ドイツでは日本の原発事故を教訓にして原発は止めたのです。
実際に事故にあった日本ではこの教訓も生かせず、また新たに稼働することにしています。一回事故が生きたらどうしょうもないことになることを経験したのに…また南海トラフの問題も抱えているのにそんなに経済発展のほうが大事なのかと思ってしまいます。
多数を占める自民党の中に政府の考えにストップをかける人がいないのでしょうか? ストップと云えない雰囲気なのでしょうか?
小泉元総理と細川元首相の意見に私は賛成です。
そこで今日の稽古は三友の式をして、皆でお花を手向け、香を聞き、お薄を頂きました。
お花は庭にある椿数種と、クリスマスローズ、水仙、アジサイの新芽、山茱萸、土佐水木等つかいました。お香は沈香。お薄4服でお菓子付。
三友の式は七事式には入っていません。円能斎が考案された七事式に準ずるものです。
普段の稽古とともに七事式も時々入れて稽古をするようにしています。
|
|
|
![]()
2015.02.18 八炉の稽古
今日は八炉の稽古をしました。
小間では本勝手向切や本勝手隅炉、または逆勝手の向切、逆勝手隅炉の茶室があります。今日庵・待庵等はその例です。
そのような極小小間で実際にお点前をする機会はめったにないと思います。しかし稽古のための稽古のようですが、頭の体操を兼ねて逆勝手点前をしました。
 逆勝手では帛紗は右に付け、出入りの足も違いますし、その他にも本勝手の時と違う点が沢山あります。
逆勝手では帛紗は右に付け、出入りの足も違いますし、その他にも本勝手の時と違う点が沢山あります。
風炉先屏風をあっちに動かしこっちに動かしながら、また畳のへりに黒や、肌色のガムテープを貼ってそれらしい部屋に設えました。お釜の向きもそのたびに変えて・・。
逆勝手向切では、①正面向いて点前をするやり方のほか、②内流し、③外流しの方法があります。
②と③では建水を持ち出したら柄杓は引かずそのままにしておいて使うときに手にして、蓋置は水指前に置くことがポイント。
実際にやってみて小間は亭主と客が本当に近く、親密さがあること実感しました。昔の人は小さかったとはいえ男の方だと点前をするのに結構狭くやりにくかったのでは?またお客様もちょっと窮屈だったのでは?と思いました。しかし、にじり口も鍵をかけヒソヒソ話の密談をするのにはちょうどよかったのかもしれませんね。
今日は非常に寒く、何時雪になってもおかしくないほどの雨日でしたが、お稽古される方は頭と体をフルに回転させて、寒さも何のそのと逆勝手に挑まれました。
時々はこういう稽古も刺激があって良いと思いました。
![]()
2015.02.11 失敗から学ぶ
先日の稽古で、建水の中に帛紗を落とされてしまった方がいました。
点前で仕舞い付けの時茶杓を清めて、建水で帛紗に付いた抹茶をポンポンとはたく時、帛紗が崩れて一部が建水の中に入ってしまったのです。
即座に同席の生徒さんが水屋からタオルを持ってこられましたが、汚水浸し。私の帛紗をお貸ししてお点前は続行しました。
一部とはいえ汚水に浸かってしまったので結局全体を水で洗いました。タオルにくるんで水分を取り、広げて乾かしておきましたら帰られる頃には生乾きながらシミになりそうもなく応急処置が良かったとホッとしました。即座に対応してくださった生徒さんに感謝です。
よく着物の袂を建水に浸してしまうことがあります。関東間の畳ですと幅が狭いので、炉の時期は勝手側がどうしても混雑します。点前を見ていてもひやひやすることがあり、つい「 袂、気をつけて]と言ってしまいます。
かく言う私も昔、炉の炭を直しているとき懐中してあった小帛紗を火中に落としてしまったことがあります。下屈みしていて小帛紗が飛び出してしまったのです。慌てて取り上げましたが、絹が燃えるにおいがして焦げてしまいました。
また後炭手前の時に、籐の釜敷きがお釜にくっついていたのか釜敷きごと炉に戻され、煙が立ちびっくりしたことがありました。
またお点前で茶入と棗を置き換えることがあります。そのとき茶杓をいったん水指の端に仮置きするのですが、その時茶杓を水指の中に落とされた方も他所で見たことがあります。急いでタオルで拭いていらっしゃいました。その席主の方は「火の中だったら大変だけれど…」と冷静にあたたかく対処されていました。蛇足ながらその茶杓、兜巾が特徴の淡々斎作でした。
失敗からいろいろ学びます。
![]()
2015.02.01 茶事二考(その2)
1月末日、昨年教授を頂いた方の茶事に伺いました。
巻紙に書かれたご案内を頂いた時、「正客に」と書かれていまして、4人の連客は存じ上げていない方々でしたので少し不安でした。
今までに稽古茶事は自宅で何回かしていますが、正式に他所で、しかもご亭主の方だけ存じ上げている環境での茶事は初めてです。しかも正客です。
しかしお祝いの茶事でありますので、お返事を認め、緊張しながらも伺うことにしました。
我が家からはかなり遠い場所で、初めて行くところなので早めの電車に乗って出かけました。幸い前日の雪と打って変わった冬日和です。
駅にはご主人様が車で迎えに来て下さっていて、はじめてお目にかかった連客様とともにご自宅へ。
寄付きには仙迆さんの絵が掛っていてほのぼの感がし、緊張もほぐれます。
路地草履をはいて腰掛待合に行くと、円座の上にはもこもこした可愛い袋が置かれています。触ると暖かい! 何とホカロンが入ってるのです。ご亭主の細かいお心遣いに感激です。
ご亭主との無言の挨拶をして、蹲を使い本席に入りました。
 「心外無別法」のお軸と、蓬莱山飾と鈴、そして結び柳。台子に皆具の設えです。
「心外無別法」のお軸と、蓬莱山飾と鈴、そして結び柳。台子に皆具の設えです。
ご亭主が入られ、一人づつ挨拶を交わします。お軸はご亭主が準教を頂いた折、御主人様から贈られた立花大亀老師の御染筆。すべての現象はそれを認識する人間の心の現れ、心と別に存在するのではない・・良い文言です。柳は昔友人から頂いた柳を挿し木したものだそうですが枝は長く畳まで垂れていて見事でした。蓬莱山飾もご亭主の手作りのものがありました。
炭手前があり、お釜は亀甲柄で環付に亀さんが可愛くしがみついています。香合は教授を頂いた折、家元から頂いたという亀甲形の楽、表には《松風聴》の文字があり、蓋裏には家元の花押が浮き彫りされています。そういえばご亭主が付けられている帛紗は緑色で、教授の証書?と共に直々に手渡しで家元から頂いた帛紗とのことでした。
懐石はこれまた素人離れした素晴らしいもの。煮物椀のふたを開けて皆様「ウワー素敵」と歓声が上がりました。花びら餅の形をしたものだったのです。八寸では手作りのからすみが出ました。生のボラの卵を塩漬けにして何週間もかけて作られたもの・・お手が込んだものばかりです。千鳥の盃もしました。
お菓子はこれもいろいろ試行錯誤で作られた菊型の練り切り。ユリ根餡も入っているのです。銀箔が上にのっていて、これは前日の雪を表現したそうです。お料理の一つ一つをご亭主自らがお客様銘々に運ばれ、さぞおみ足が痛くなるのではと申し訳ない気持ちです。
中立ちして又腰掛待合で先ほどのホカロン袋で暖かく待ちました。銅鑼の音で後入り。いよいよお濃茶です。嶋台でおいしいお濃茶頂きました。茶名は柳桜園の「鳳」おおとり。師が好まれていたというお抹茶だそうです。師への尊敬の念を感じるご亭主のお人柄が分かるようでした。
お道具はいろいろお人とつながるお話のあるものが多く、今まで茶道をされていた中で培ってきた人間関係をとても大切にされていること強く感じました。
薄茶はご亭主も加わって《員茶》をして、代わり代わり薄茶を頂きました。朝から我々のために大変であったご亭主にせめてものお返しにと、私は亭主役をしました。
つまるところ、茶事は人と人とのコミュニケーションが肝心で、今回はご亭主のお人柄に加え、茶事が進むにつれ すっかり打ち解けた連客様と気持ち良くコミュニケーションが取れたことで、和やかで楽しい素敵な一期一会でした。
思いがけない出会いで、面識のなかった方々とのつながりが茶事を媒介に出来てしまう茶道の素晴らしさを再確認しました。
帰宅して早速、その余韻が薄れないうちにお礼状を書きました。
茶事二考として(その1)(その2)を書きましたが、先回の茶事(その1)は茶事の勉強をしながらも、おもてなしを受けたお姫様になったような幸せ感たっぷりの茶事だったような気がします。亭主との挨拶も正客が代表でなさり、またお礼の手紙を書く必要もなかったので気楽なものでした。
そして今回(その2)の茶事は、亭主を存じ上げているので、連客の皆様共々心を通い合せ、茶事にしっかり「参加した」という充実感のある茶事でした。
茶事もいろいろです。
![]()
2015.02.01 茶事二考(その1)
この1月、茶事に2回伺えるという機会を頂きました。
ひとつは ある茶友仲間とご一緒に行った茶事を専門にされている場所での茶事。もうひとつは ネットでお知り合いになった方のお宅での茶事で、その方が教授を頂いたとのことでの茶事です。
今回はひとつめの茶事について書きます。
お客は10人。亭主はその席主の方で、茶道・日本料理・香道のプロの男性。昭和初期に建てられたという懐かしい間取りの家です。しかし畳の良い香りがして新年を実感します。
新春の茶事ということで寄り付きは干支の羊の絵が掛っています。画賛として「徳如恙羊」。煙草箱、手焙りは時代物という感じ。白湯を頂いて腰掛待合へ。そして蹲を使い本席へ。
床は狩野派の宝船の絵に「知足こそ心の宝・・」と云った文言が書かれた江戸後期のもの。立派な蓬莱山飾に結び柳。炭手前では上張環付のお釜でトンボ環を初めて拝見。羽はブルーでインコの羽。香合は羊絵リモージュ。どれも目を見張ります。
懐石はさすがに本職の日本料理。煮物椀は素晴らしい味付け、珍しい食材もあって美味しくいただきました。 ふわっとした《羊きんとん》を頂いて中立ち。
ふわっとした《羊きんとん》を頂いて中立ち。
銅鑼の合図で後入り。唐物の大海茶入に、華奢な茶杓。”これぞお濃茶”というしっかりとしたお濃茶を頂きました。亭主の方の大変さっぱりとした男点前も好感が持てました。
後炭は略され、薄茶点前に。棗は日の丸型で緑の地に、金色で世界地図が描かれています。このような珍しい棗も初めて拝見しました。
いろいろ珍しいお道具、おめでたい意匠や干支意匠など新春を堪能しました。
最期に福引のお楽しみもあり、参加した我々は、一日素晴らしいおもてなしを受けたお姫様のような気持になりました。
正式な茶事の流れを実体験でき大変勉強になりました。

2015.01.24 初茶会へ
茶友の茶会に行ってきました。川崎大師で行われる淡交会川崎支部茶会で薄茶席を持たれるのです。
今年一番のお茶会への外出ということで生徒さん二人とともに華やいだ気持ちで参加しました。
 まだ1月なので川崎大師は参拝客の多いこと、多いこと! 参道にはダルマを売っているお店や、くずもちのお店等呼び込みも盛ん。境内にも屋台が沢山軒を並べ、護摩焚きのけむりに満ちています。
まだ1月なので川崎大師は参拝客の多いこと、多いこと! 参道にはダルマを売っているお店や、くずもちのお店等呼び込みも盛ん。境内にも屋台が沢山軒を並べ、護摩焚きのけむりに満ちています。
お濃茶席は時間指定です。寄り付きで花びら餅を頂きました。床中央には掛け花入れがあり、白い侘助と紅梅が珍しい竹の花入れに入れられてます。
こんな珍しい竹はきっと外国の竹かしらなどと話しているうちに本席の大広間へ導かれました。
床には大亀老師の《山呼万歳声》に蓬莱山飾、見事な寒牡丹が染付の扁壺花入れに・・柳枝が天井から豪快に流れています。
お濃茶は全員嶋台で頂きました。嶋台の高台が銀の茶碗は六角形の亀甲の形をしていて、金の茶碗は5角形で鶴を表していること初めて知りました。お道具もおめでたい意匠のもので取り合わせられ新春ならではです。福引もあり楽しい席でした。
続いて薄茶席に誘導されます。ここは和親棚で足に優しい立礼席。床には鶴亀を読み込んだ素敵な字体の懐紙が掛けられ、打ち出の小槌香炉、白玉と紅梅がきれいな緑釉の花入れにはいっています。
登り亀平棗、鶴首釜、淡々斎が家元になって初めての初釜で削られ福引になったという《福笑い》茶杓。お菓子は珍しい茶臼形の打物干菓子。それにお薄を頂いたお茶碗をのみ終えると見込みに大吉・吉・中吉・末吉の文字が…。またここでも楽しく盛り上がり、とても和やかなお席でした。
両方のお席の正客の方は85歳を超える年齢のおばあ様でした。足腰は弱られていらっしゃるものの、きちんと訪問着を召されてお茶席までお出かけになられ、正客としてのはたらきをされるお姿がとても印象的でした。「茶是長寿の友」という文言が私の頭に浮かびました。
今回は新春ということでおめでたい設えを本当に堪能しました。何か心も華やいで、今年も良い年になるような予感すら感じました。
帰りは本殿にお参りをして、楽しかった茶席の余韻を楽しみつつ、家路につきました。
追記:ネットで調べると、寄付床の竹の花入れ…亀甲竹といって日本にもある竹のようです。

2015.01.10 初釜
天気に恵まれた今日、初釜をいたしました。今年からは時間厳守を徹底したいので、「10時に開始」と皆様に予め厳しく言っておきましたので、集合が早かったです。
今年は参加者が多かったので「重ね茶碗」で私が点前で濃茶を2碗練り、後は水屋係りの方々に3碗陰点てで練っていただきました。重ね茶碗は普段の稽古ではなかなかできない点前なのでお客様もちょっと戸惑った感がありました。
重ね茶碗で7人分なので、茶入では抹茶がいっぱいになってしまいます。そこで「包帛紗」で行いました。包帛紗はこういう時にも便利なお点前です。
炭はあかあかと熾っていてお釜の煮えは上々、おいしいお濃茶が練れたと思います。10時開始を逆算して火を熾し、釜をかけたのでとても良い感じです。やはり時間を厳守してもらうとお客様を迎える側にとっては気持ち良いことです。
濃茶の後は恒例の”お楽しみくじ”です。生徒さんからの差し入れもあったので、今回は外れ無しのくじです。帛紗、扇子、楊枝入れ足袋カバーなど・・。毎年どういう風にするか考えるのは私にとっては楽しいことです。今年は数をイメージできる絵を描いたカードを引いてもらいました。
その後は水曜クラスと土曜クラスの新年顔合わせ会です。ちらし寿司とちょっとしたおかずを用意しました。日本酒で乾杯して、あとは和やかに歓談。お正月に帰省された方、インフルエンザにかかって家で過ごされていた方、お孫さんや家族と過ごされた方などいろいろでした。
この新年会もあまりダラダラ長くしてもよくないので、午後1時にはお開きにしました。
お開きの後、私はまだお釜の煮えがあったので、薄茶を点てて、今年も皆様と初釜ができたことに満足感を持ちつつ静かに頂く独服、こういう時間が私は好きです。
そして、着物を着換えて、火の始末、茶道具の始末、食器洗いなど済ませましたが、終わったのはまだ午後2時半でした。私も70代に入ったのでなるべく疲れないように気を付けたいので、今日の初釜はその意味でもすっきりしてよかったと思います。
今年も皆様と一緒に茶道に励みつつ自己研鑽したいと思います。
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
||

















