![]()
new2015.12.28�@ ���N��U��Ԃ���
�u���N���N�@�т��_�̂��Ƃ����́v���q
�l�Ԃ��X��������ƁA�u���悢�捡�N�����Ɛ����v�Ƃ������ł����A���R�E�̒��⓮���A�A���͍��܂Œʂ�̒����������ė[�������ޓ��X�ł��B�I�������߂�����܂���B
��������X�͈�N���I�����Z�b�g���āA�V���ȋC���E��]�������Ď��̈�N���}����̂ł��B���̈�N�́s�\��j���[�X�t�Ƃ��s���N�̊����t�����̔N�����ĐV�N���}���܂��B
�����Ŏ������̈�N�̒��������ɂ��ĐU��Ԃ��Ă݂܂����B
���N�͂��̒��������ŏ��߂āu�����v��q�ꂽ�������炵�����ƁA�܂��u�s�̐^��q�v�܂ŋ���������������������炵�����Ƃ͎��ɂƂ��ĂƂĂ����������Ƃł����B
�܂��A�В��Ŏ��̌Ê���j���ċ���ŐH������Â��Ă������������Ƃ��T�v���C�Y�Ŋ��������Ƃł����B
�m�Â̂ق��͐��k�����\����������̂ʼnԌ������낢��m�Â��ł��A�܂�������O�F�̎��Ȃǂ��ł��܂����B
��̂��_�O���ł�������������̂Łu�s�̍s��q�v��u�s�̐^��q�v�Ȃǂ̓��ʌm�Â����x���ł��܂����B8���͍��N���߂Čm�Â��x�݂ɂ��Ă��܂��܂���������͂�����Ɣ��Ȃł��B�����Ƃ��͂���Ȃ�̌m�Â��ł����̂ɂƎv���܂����B���������̊Ԑ��k����͔��p�قɍs������A���Ɋւ���{��ǂ莩��I�ɕ������ꂽ�悤�ł��B
11���E12���͎�l���v�������Ȃ��̒�������A�m�Â��ł��Ȃ��Ďc�O�ł����B����Œ����������ł���̂������ƉƑ������C�ł����Ă̂��ƂƂ��������v���m�炳��܂����B
��l�̑̒������N��������Ǝv���Ɨ�⊾�ł��B���N�s�Ê�t���ł������Ɩ{���Ƀ��b�L�[�ŗǂ������ƗL���C�����ł��B
�l���͕s�����A�����N���邩�킩��Ȃ��̂ŁA��肽�����Ƃ͏o���邤���ɂ��A���̓����̓����ɐ���t�����Ă�����������܂���ˁB
![]()
2015.12.14�@ ����
���ĂƂ����ƑT�m�̐��E�����̂��ƂƎv���Ă��܂����B���Ă͑T�@�ɂ����ďC�s�m�������J�����߂̉ۑ�Ƃ��ė^��������̂��Ƃł�����B�Ⴆ�s�ǎ�̐��t�Ƃ��������Ăł��B
������C�Ȃ��s�u(�����d�e���u������̎���v�������悤�ȁH�j�����Ă��܂����瑂���@�̂��炢�m���̕������b������Ă��܂����B
�����ň�ۂɎc�������Ƃ́A���������������ɂԂ������Ƃ��͂��ꂪ���̐l�ɗ^����ꂽ�s���āt�Ǝ~�߂�悢�c�̗l�Ȃ��Ƃ�����������Ă��܂����B
������ās���āt�Ƃ����͉̂����T�m�����̂��̂ł͂Ȃ��A��X�����X���Ă�^�����Ă��āA����Ȃ�ɍl���Ă���̂��Ǝv���܂����B
�Y�݁E����̎����N�������s����͎��ɗ^����ꂽ���ĂȂ̂��t�ƁA��������l�������Ȃ�̓������o���Ƃ������Ƃł��傤�B
���Ăɂ͐����͂Ȃ��A���̐l���n�l��������ɏo�����l���������Ƃ������Ƃł��B
�T�̐��E�ł́A�ꂵ�݂͑��݂��Ȃ��B���̐l���ꂵ�݂Ǝ~�߂邩�ۂ��E�E���ׂĐS�݂̍�l�Ƃ����̂ł��B�Ⴆ�R�b�v�̒��ɔ����̐��������Ă���Ƃ��āA����l�́s�������������Ȃ��t�ƍl���A�܂�����l�́s�܂������c���Ă���t�Ǝ~�߂�Ƃ������悤�Ȃ��̂ł��B
�܂�Ƃ���A��₪�~�肩���������́@�l�̂����ɂ�����A�V�����ނ��ƂȂ��A�ǂ���������������悢�������ōl���Ď����œ������o���E�E�E�����̐S�݂̍�l�������ŒT��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�����͈̂Ղ����s�͓���ł����B
���̂Ƃ���A���̌m�Â��牓�������Ă����̂ŁA�Ȃɂ��N�w�I�Ȃ��Ƃ��肪�E�E�E�B
![]()
2015.12.02�@ �y�b�g���X�Ȃ�ʁ@�������X
�킪���������̓y�j�N���X�͌�2��̌m�Âł��B�����ł��܂��܂��̗����Ƃ����s���������ƁA1�����x��ł��܂����ƂɂȂ�܂��B
���k����̂��������s�挎��������m�Âł����A ��������Ǝv���܂�����A�ނ��傤�� ���m�Â��������Ȃ�܂����B ������Ƃ����y�b�g���X�Ȃ�ʁw�������X�x�݂����ȗ҂��������ł��B�t�Ƃ������[�����������������Ƃ�����܂��B
�s�������X�t�E�E�E�E���߂Ď��ɂ��܂������A�������Ė��ł��B�����܂Œ������y�����v���Ă�������Ƃ͂ƁA���̓��[�������Ċ����������܂����B
���A�������̏�ԂɂȂ��Ă��܂��B
10�����ɁA��l���̒����Ď�p���邱�ƂɂȂ����̂ł��B����ł�����A��ϐS�z�ł������A�K��������p�͐������܂����B������������n���Ȃ̂ŁA�オ��ςł��B
�����ł킪����������2�P���x�܂��Ă��炢�A��l�̐��b�A���ɐH���Ǘ��ɌX�����Ă��܂��B�悭����ŏ��ʂ�����ɂ������ĐH�������܂��B��l�͐H�ׂ邱�Ƃɒǂ��Ă���悤�ŁA�H�ׂ�̂ɔ���ƌ����܂��B�v���悤�ɐH�ׂĂ��炦�Ȃ����������ł��B
�܂�ŁA�q���������Ԃ���������̗����H���ƁA��������������̂ɐH�ׂĂ��炦�Ȃ��������̂悤�ł��B
���̂悤�Ȃ킯�ŁA�������x���2�����c���N�̊��x�̒��q��������������̂ɂƁc���낻��s�������X�t�̋C�����ɂȂ��Ă��܂����B
�����̌m�Â��ł���Ƃ������Ƃ́A�Ƒ��⎩�������N�ŁA�K���̎��Ƃ������Ƃ����Â��v�����̍��ł��B
![]()
2015.11.03�@ ��l��
���|���Ɂs��l���t�Ƃ����̂�����܂��B
���ʂɎ�l���Ƃ����h���}�E�����ł�������̒��S�l�����w���܂��B
�������A����͑T�̌��Ă̒��̌��t�ŁA�{���̎��ȁE�^���̎��Ȃ����Ӗ��ł��B
������̐����t�F�a���i�����������傤�j�����X��������߂����t�B
�a���͎������g�Ɂu��l����v�ƌĂт����āA�u������������ڊo�߂Ă��邩�v�A�u�͂��ڊo�߂Ă���܂��v�Ǝ��⎩�����������ł��B
�l�͂�������������g�ɂƂ��Ă̎�l���ł��B
����ǎ��ɖ����A�������������B�����炱����Ɏ������g�ɌĂт����A����ɓ����Ė{���̎����A�������g�̂���ׂ��p�������ƌ��߂邱�Ƃ��厖�Ƃ����킯�ł��B
���������Ƃ��N�������A�s���ȋC�����ɂȂ������A�{�肽���Ȃ������A���炢�炵�����A����ȍl�����N���o�Ă������E�E�E�E�����������@���Ŏ����̊������Ƃǂ��ł��傤�B�����ƋC���������ɕ\��Ă��邱�Ƃł��傤�B�������Ȃ��Ă��z�������܂��B
���̎������u������l����v�ƌĂт����A�u�炪�ςɂȂ��Ă��邼�v�u�͂��A�ςł��B�悩��ʂ��Ƃ��l���Ă��܂����B�v�Ǝ��⎩�����āA�����̐S��{���̎��Ȃ̎p�ɖ߂��A�������g�̂���ׂ���Âȍs�����m�����邱�Ƃ��ł���悢�Ǝv���܂��B
![]()
2015.10.3�@ ���t�Ԍ�
���k����̏K�n�x���オ���Ă����̂ŁA���̍��͂��낢��ȉԌ����y���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
���T�́s���t�Ԍ��t�̌m�Â����߂Ă��܂����B
����͂������R��ޗp�ӂ��āA�y���z�ɓ��������������̒���������I��ŕ����܂��B���̍����F����������A������m��܂��B���̌㕽�Ԍ��̂悤�ɔ������R���_�āA�����čŌ�ɍ����Ɉ��́k�a�̂ł��o��ł��悢�l���I����Ƃ����A�Ȃ�Ƃ���тȂ��̂ł��B
�����Řa�̂��r�ނ̂͑�ςȂ̂ŁA�O�̏T���獁���͊F�l�ɓ`���āA�̂��l���Ă��Ă��炤�悤�ɂ��܂����B�ŏ��͊F����u�����a�̂ł����v�Ƃ��u���܂ł��悢�ł����v�Ƃ����������Ȃ�����A������Ɗy�������ȕ��͋C�B�����́s�P���t�Ƃ��āA���H�̖����̎����ł��������̂Ō��Ɉ��̂��Ƃ������Ƃɂ��܂����B
�ɖ��X�M�ʼn̂����������A�ꉞ�M�y�����p�ӂ����̂ł����A�F�l�͖{�i�I�ɖn�ƕM�ŏ�����܂����B
�̂����ꂼ��C����f���ɉr�܂ꂽ���̂�A���l���̕�����ǂ��a�̂���ł����B
�����E���E�a�̂��R���{���[�g�������̂ŊF�l�傢�Ɋy���܂ꂽ�悤�ł����B���Ԃ��]�����̂ŁA�������݉Ԍ����y���݂܂����B
|
|
|
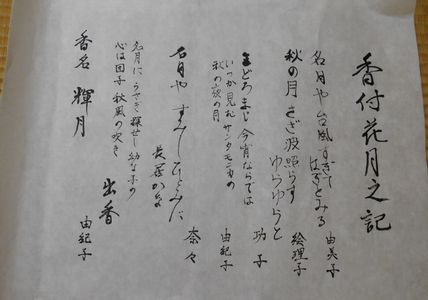 |
 |
 |
 |
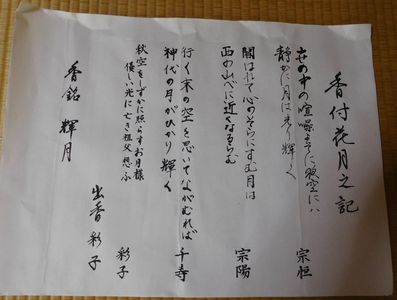 |
 |
![]()
2015.09.01�@ �H�̎���
���N�͏H�̓����������A���̂Ƃ���J������22���ʂ̔��������������Ă��܂��B���K�Ƃ����悢�̂ł����A�����ُ�Ȋ����ł��B
�H�̎����̒��́s�j�[�t�����Ȃ̐�Ŋ뜜��U�ɁA�s���сt������Ŋ뜜��ɓ����Ă��邱�ƁA���W�I�Œm��܂����B
�͌����q����Ȃ������ł��B���͉��|�킪����܂����A��������{�ݗ��킪���b�h�f�[�^�[���X�g�ɓ����Ă���̂ł��B
�����̑��Ԃ͐l���߂��̑��ނ�ɐ�������̂ł����A���̑��ނ炪�����Ă���̂ł��B�͐�H���E�c���̐����E��n�����A�����g�p�Ȃǂ������������ł��B
�a�̂ɂ������r�܂�Ă��āA���t�̂��납��ߐ��ɂ����Ă͂�����ʓI�ȑ��Ԃł����������A�����͏H�ܑ̌��ɂȂ��Ă��܂������c�B
���������H�̎����������Ȃ����̂͌Â��R�㉯�ǂ̘a�̂���ŁA�h�H�̖�ɍ炫����Ԃ��w�܂�ӂ�@����̉ԁA���̉ԁA���ԁA���ԁA���q�̉ԁA���Y�Ԃ܂����сA����̉ԁh�̂͒��炾���������ł����j�[�Ǝ��Ă��܂��B
���a�̏����ɂ���V���Ђ��L����ƂɂЂƂÂI��ł�������V�H�̎����Ƃ����̂����邻���ł��B����̓R�X���X�E�I�V���C�o�i�E�q�K���o�i�E�V���E�J�C�h�E�E�n�Q�C�g�E�E�L�N�E�A�J�}���}�B
�����͍��g�߂ȑ��ԂŁA�����I�ł��B
![]()
2015.08.23�@ ��������Ȃǂ̐���
�W�������ɏo�Ȃ���悤�ɂȂ��Ďl�����I�B
���[�搶���璼�ڂ��b���f����B��̋@��ł��B�N4,5���Ȃ����������̕��̉�B�u�s�������v�ʼn��ł͂��܂胁��������Ă͂����Ȃ��Ƃ����܂����A���͂�����Ƃ������Ƃł����������܂��ƃ��������܂��B�����Ă��̏�ł͂킩���Ă��Ă��Y��邩��ł��B
���̃������ƂɋA���Ă����̑I�����ăm�[�g�ɏ����Ȃ����܂��B���̃m�[�g��10�����܂����B���X�������A����ς胁�����Ă����Ă悩�����Ǝv�����Ƃ������ł��B
������ł̋��[�搶�̍u�`�͋����@�̃q���g�Ƃ��Ă��A���k��������������鎄�ɂ͑傢�ɖ��ɗ����܂��B
���̉ċx�݂ɍ��܂ł̃m�[�g��ǂݕԂ��A�������܂����B�_�O�A����A����ɂ��Ă��낢��ĔF�����邱�Ƃ����������ł��B��ꂪ�Ճm��z�[������A��؏@�ێ��E�����@�����E���R�@�����E�q�l�@�o���E�i��@�\���Ȃǂ�������������[�搶������̍u�`�����͉��������ł��B
�܂��A�G���s�W���t���C�ɓ������ӏ����v�����ăJ�b�^�[�Ő����ăt�@�C�����A�{�͎̂Ă܂����B�������Ŗ{�I���������肵�܂����B
�܂��A������̐����E�����̐��������āA�Y�������Ղ����9������̌m�Âɔ����邱�Ƃ��ł��܂����B
���܂ɂ͂��������܂Ƃ܂����x���͕K�v�ł��B
![]()
2015.08.10�@ ��ؑ�ْ��u�T�Ɠ��{�����v��ǂ��
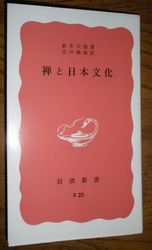 8���͌m�Â��ċx�݂ɂ��܂����B���̖ҏ��Ɂ@�������Ȃ��ŋx�݂ɂ����ق����悢�Ɣ��f���܂����B
8���͌m�Â��ċx�݂ɂ��܂����B���̖ҏ��Ɂ@�������Ȃ��ŋx�݂ɂ����ق����悢�Ɣ��f���܂����B
���k������ɂ͏h��ł͂Ȃ��ł����A���̋x�ݒ��ɒ����Ɋւ���{������ł��悢����ǂ�A�܂����p�قŒ�����̈�ł��悢���猩�Ă��Ă˂ƌ����܂����B
���͂����Ɛϓǂł�������ؑ�ْ��E�k�쓍�Y��u�T�Ɠ��{�����v�̖{�����������ɂ��������ĐԂ����M�Ő��������Ȃ��牽�Ƃ��ǂݏI���܂����B
���̖{�͂��Ƃ��Ɖp��ŏ�����Ă��āA�O���̕��ɕ������u�`���邽�߂ɏ����ꂽ���̂ł��B�u���̖{�v���p��ŏ��������q�V�S�Ƃ����f���炵���p��͂��������������̎���ɂ�������Ⴝ���Ƃɂ͋����܂��B
�܂���1�͂͑T�̗\���m���A���Ƃ͑T�Ɣ��p�E�T�ƕ��m�E�T�ƌ����E�T�ƎE�T�ƒ����E�T�Ɣo��̏͗��ĂɂȂ��Ă��܂��B
�T�̗\���m���ł́A�T��8���I�����Ŕ��B���������B�T�̈ꕗ�ς�����b�B�@�́@�^�����ǂ�Ȃ��̂ł��낤�Ɛg���Ȃ��đ̌����邱�ƁB����䂦�T�̃��b�g�[�́s���t�ɗ����!�t�s�������B�̌����Ē��o�I�m�����Ăъo�܂���Ƃ�����̂��T�ł���B
���͒��������Ă���̂őT�ƒ����̏͂ɂ��Ă�������ǂ݂܂����B
���͑T�m�ɂ���Ă����炳��A���������A��X�̕a�Ɍ����ƍl����ꂽ�B���͐S�_��u���ɂ����邪�����͂����Ȃ��B
�h�����剞���t����x��������Љ��Ƒ����A���x���Ō�̎d�グ�����A���̒��̓��itea-cult)�ƂȂ����B
���́u�a�h����v�̐��_�͑T�̐��_�Ɩ��ڂȊ֘A������A����͑T���̐������̂��̂ł���B
�������q��604�N�s�a���ȂċM���ƂȂ��@�w�i�����j��ӂ��ƂȂ����@�Ƃ��t�Ɖ]�����悤�A���{�l�͑S�̂Ƃ��ĉ��a�Ȑ����̍����ł���B�������Љ�I�����I�ȓ��ɐڂ���ɂꂱ�̓��{�I���i���炻��₷���Ȃ�B���������Ă����̂��T�́h����Ȃ����S�̏_�h�B
�����̕��͋C�͘a�����͂ɂ��肾�����ƁA���͏_�炩���ґz�I�ȋC���ɗU�����ށB�S�̐������͒��ɂ�����h�B�����E���ڂ͒��̐��B�m���̖��n�̚g�����Ƃ��̕n�R�̔��I��E�s���S�Ȃ�������̎�B
���͎��R�ƈ�ɂȂ肽���Ƃ����S�̉���ɂ��铲�ۂ̔��I�\���ł���B���͒P�ɗV�|�ɂ��炸�A���Ɠ�����_���Ƃ��n�������Ă����B�����̂̒��l�͐^�ʖڂɑT���C�߂Ă����B
�ȏ�ȒP�ȊT���������܂����B
���݁A�����̌m�Â͓_�O������A���������A���������鎖�����œ����C�߂�ƍl�������ł���B��ʂ̉�X�͎Q�T�Ȃǂ̋@��������܂��A�u���T�ꖡ�v�Ƃ����đT�̐��_�E�C�����������ď��߂ėV�|�łȂ����ɂȂ�܂��B
���́s�a�h����t�Ƃ������t�͒m���Ă��Ă��A��������H���m�Â����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�s�a�h����t�Ƃ������t�̉��[���Ӗ����ĔF�����܂����B
![]()
2015.07.16�@ �`�������l
�킪�В����o�����������ŁA�����ƌ��Ă����s�u������w�s�p��ŕ`�����{�t������lesson
15�ŏI�����܂����B
�u���E�J�����O�搶�����{�̓`�������i�����E�����E���C���E�`���v�E���Αł��E���E���ԁE�����E�����E���T�E�a���ہE�d���E���t���E�������E�͌�j�����ׂĎ��ۂɑ̌����Ċ��z���q�ׂ�Ƃ����ԑg�ł����B����قǑ�����̌��ł����O���l�͂��Ȃ����낤�A�ƂĂ����b�L�[�������Ɛ搶�͌����܂��B����{���Ɉꐶ�������킳��Ă��܂����B�����ă|�C���g��t�������������Ă��܂����B���{�l�ł��鎄���ڂ���̂悤�Ȃ��Ƃ��w�ׂ܂����B
�ŏI��̍����́@���܂ő̌��������̂���A���{�̓`�������ɋ��ʂ��������A�u���E�J�����O�搶�̊������s���{�̐S�t������܂����B
���{�̓`�������̓��������̂悤�ȍ��ڂŐ�������܂����B
1�j��Ɏn�܂��ɏI���
�@�m�Â̏��߂ƏI����������肳���A���킩�������ւ���B��q��O�ɒu���h�ӂ�\���đ���ɗ������B�m�Ï�E��������Ȃ�ꏊ�Ƃ��ē��鎞�E�o�鎞��炷��B
2�j���K�̑��
�@�h�K�����������h�u�Ƃɂ����g�ɕt���܂ł��Ȃ����B�����͌ォ�番���邩��v�ƁA�Ђ�����m�Â��J��Ԃ����K������B�č��ł͂܂��ڕW���߂ė��K������B
3�j�W���A���S�ł���
�@�u�����l���Ȃ��Ŗ��S�łȂ����v���z�I�ȐS�̂�����E�C�����̂�������C�s�̈ꕔ�Ƃƍl����B
4)�^�̒��ł̎��R
�@��������^����邱�Ƃ��d���B������������x�܂ōs���Ǝ��R�x�����������̂�����
5)���퐶���ւ̉��p
�@�m�Â����邱�ƂŁu�@���ɐ����邩�@How to live�v���w�ԁB
�u���E�J�����O�搶�͐��X�̓`��������̌�����A���̐[���ɋ����A�،h�̔O������ꂽ����A���܂����^��������Ǝ�点�邱�Ƃ͌��ꂵ��������Â����������邪�A�����ɉ��l�����o���Ă���̂��`�������B���̂����肪����ł͓��{�l�ɉ��������Ă���̂ł͂Ȃ���?�@��������{�͊�{�Ƃ��Ȃ��������ł��y���肷����@����������Ői���͂��Ă���B
�`�������͓��{����{���炵�߂Ă���Ǝv���B���{�̓n�C�e�N�Ń��_���ȍ��ł��邪�A���������`�������̋��݂�m�邱�Ƃ���ŁA������w��ŊO�֔��M����R�~���j�P�[�V�����͂�{���Ă��炦����悢�Ǝv���ƌ���܂����B�����m�邱�Ƃ��A������m�邱�Ƃ��厖�Ƃ������܂����B
�ǐL�F�F���̔ԑg�͍���7��22������29���܂łP���Q lessons ���ċG�W�����Ƃŕ��f����܂��B�n��f�W�^���P�Qch �܂���BS231-232�@���Ԃ� 16�F45����18�F00
![]()
2015.07.04�@ ����`�B��
�u�^�̍s��q�v�̋���������̓`�B�������܂����B
��͂肱���܂ł���ꂽ���ɂ͂�����Ƌ�������n���������ƁA�m�Ó��Ƃ͕ʂɁA�������������̕��̓��Ȃ����肢���čs���܂����B
�������ۂɓ_�O������̂��ǂ��̂ł����A���Ȃ������̗��K�ɂ��Ȃ�̂ł��̕��ɂ��Ă��������܂����B���̂��Ƌ���`�B�������āA�������̂��_�O�����m�Â��Ă��������܂����B
���܂ł̂��_�O�Ƃ͈��������E�������o�Ă��܂����A��͂�l�P�`�E�s�̍s��q�E�~���ƌm�Â��d�˂Ă���ꂽ���Ȃ̂ŁA�܂��܂��̏��m�Âł����B
���̌�́A�����̂��ŏj���̑V���݂͂܂����B
��t�p�Ŏ����X�������邱�Ƃ͑�ł��B ������Ƃ����`�B�����o�����邱�ƂŁA���炽�߂Ă܂����i���Ă������Ƃ���C�������o�Ă���Ǝv���܂��B
������Ƃ����`�B�����o�����邱�ƂŁA���炽�߂Ă܂����i���Ă������Ƃ���C�������o�Ă���Ǝv���܂��B
 �킪�В�����A����͒������A����͐^�̍s��q���������o�����Ƃ͂ƂĂ����������Ƃł��B��l�����I�܂��ɒ����������n�߂������ɂ́@�����܂ŏC�s��i�܂������o�邱�Ƃ͖��ɂ��v���܂���ł����B�ł�����ƂĂ����S�[���̂ł��B
�킪�В�����A����͒������A����͐^�̍s��q���������o�����Ƃ͂ƂĂ����������Ƃł��B��l�����I�܂��ɒ����������n�߂������ɂ́@�����܂ŏC�s��i�܂������o�邱�Ƃ͖��ɂ��v���܂���ł����B�ł�����ƂĂ����S�[���̂ł��B
�h�m�ÂƂ͈���K���\��m��A�\��肩������Ƃ̂��̈�h
�\�܂Ői�܂ꂽ�����s����ł����悢�t�Ƃ����̂ł͐i���͎~��܂��B�܂����S�ɂ������āu���Ɓv�ɂ��ǂ�c���������́u���Ɓv�͏��߂́u���Ɓv��莟���͍����͂��ł��B
![]()
�@HOME


